一級建築士、宅地建物取引士。
多くの大工棟梁を育てた工務店の三代目として育つ。家業をベースにした「地場工務店を経営する一級建築士事務所」として多様な暮らしに寄り添った家づくりを実現。「住まう人のやりたいをかたちに」を経営理念とし、家の設計から新築やリフォームの建築工事までをワンストップに取り組む家づくりに詳しい専門家。
家づくりにあたって知っておくと役に立つのが工法に関する用語です。家の工法とは骨組みの仕組みであり、工法がわかればその家の構造や建築の仕組みがわかってきます。日本の家の工法は種類がかなり多いため、工法に関する用語は複数回に分けてお届けします。
小林桂樹2025/04/23

実は間取りが自由で、増築や改修もしやすい日本の伝統工法
33)木造[もくぞう]
日本でもっともポピュラーな建物のつくり方。その歴史は千三百年を有に超えている。公共の建物や商業施設の外壁や内装に印象的に使われることが多い。

34)木造軸組在来工法[もくぞうじくぐみざいらいこうほう]
木材で「土台」「柱」「梁」等の骨組み(軸組)をつくる工法。他の工法と比較して、外観や間取りが最も自由で、増築・改築・改修・移設がやりやすい。いろいろな木材の選択の巾が大きいので、内部外部共に仕上がりの違いを楽しむことができる。昔の建物で馴染みがあるのが、「書院づくり」と「寝殿づくり」と「数寄屋づくり」、そして「本化粧づくり」。

35)寝殿[しんでん]づくり
平安時代に完成された家の形式で、平等院鳳凰堂が代表格。畳は板の間の上に「島」のように置かれていた。

36)書院[しょいん]づくり
寝殿づくりが簡略化されて桃山時代に完成した家の形式。畳が部屋に敷きつめられ、角柱の間に障子がつくられるなど、現在の「和室」の原形ができた。

37)数寄屋[すきや]づくり
茶室建築の手法を採り入れた家の形式。飾り気がなく質素なつくりが特徴。

38)本化粧[ほんげしょう]づくり
特に屋根まわりのつくりが豪華で、「入母屋」が特徴のどっしりした建物になる。特に「軒天」を見上げると、細い棒(化粧垂木)が規則正しく並んでいて、建物全体が「見て楽しむ」出来映えになっているのが特徴。

【関連記事】納得できる「家づくり」用語集
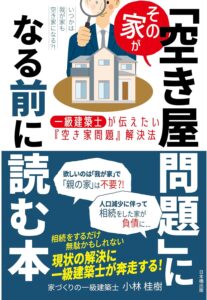
この記事を書いた人

小林桂樹株式会社パウムテック代表取締役
一級建築士、宅地建物取引士。
多くの大工棟梁を育てた工務店の三代目として育つ。家業をベースにした「地場工務店を経営する一級建築士事務所」として多様な暮らしに寄り添った家づくりを実現。「住まう人のやりたいをかたちに」を経営理念とし、家の設計から新築やリフォームの建築工事までをワンストップに取り組む家づくりに詳しい専門家。
※このサイトは「事業再構築補助金」を活用しています