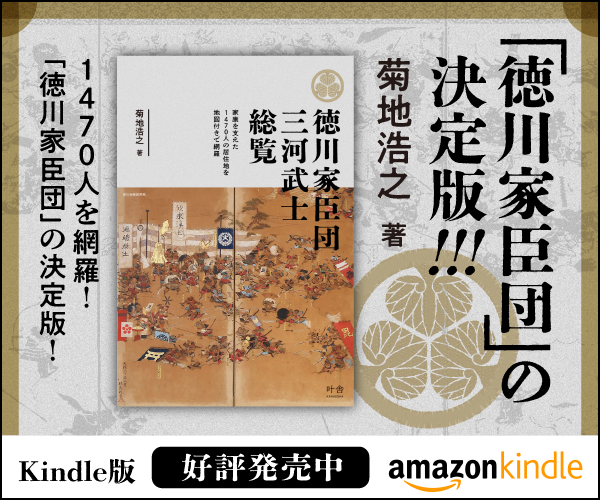1945年新潟生まれ。
中央大学商学部卒業後、東京重機工業株式会社(現株式会社ジューキ)入社。退社後は、企業の倒産現場に数多く立会い、企業の倒産回避のノウハウをマスター。1995年設立のTSKプランニングで、コンサルタントとして経営危機に直面した企業の倒産回避および事業再生に関するコンサルティングを手掛けている。
著書に『隣の会社「なぜ?」潰れないのか』『脱常識のしたたか社長論。』『日本が潰してはいけない会社』など多数。
実はIT化、DX化が進んでいる不動産業界
不動産業界はIT化、DX化が遅れているといわれますが、実は対顧客サービスという点においては逆に一番進んでる業界といえます。そのためこの流れに乗れない事業者、事業規模の格差によって、より一層、業界内の新陳代謝が激しくなっています。
当たり前のことですが、ビジネスは常に変化してます。 これは不動産業も同様です。
ここで私が懸念しているのは2027年から2040年にかけて、わが国の労働人口は急激な減少期に入るという点です。そうなれば当然、勤務スタイルも変わってきます。また、外国人労働者の受け入れや、移民についても、この時期あたりから、いま以上に真剣な議論が迫られる必要が出てきます。
もちろん、不動産業界も人手が必要な業界ですから、人の取り合いが激しくなり、おのずと生き残る会社と、淘汰される会社に一層、二分化されことが予想されます。
すでにはじまりつつありますが、大手業者では、優秀な人材を確保するために、自社が管理している高級賃貸物件を社員に貸したりしています。
また、大手は生き残るために新築10年未満の築浅物件をいかに多く管理していくかに力をいています。同様に中小不動産事業者や駅前の不動産店にとっても、仲介だけでなく、管理物件もとれなくなってくる見られ、さらに状況が厳しくなることが予想されます。
日本経済の先を見極めるバロメーター

私は地域密着型の街の不動産店というの必要だと思っています。
私自身も都内で暮らしているいますが、周辺では自分の家やマンションを人に貸したいと考えている人が多くいます。そういう人にとっては地域の不動産店は必要な存在です。
というのも、気軽に話ができれる いわば地域密着型の街の不動産店というのはとても大事です。
賃貸管理は、仲介だけでなく、家賃の回収、物件の補修、清掃といった日常業務を街の不動産屋さんが担っている部分もあります。そして、そのことが街の不動産店が生き延びてきた一つの大きな要因でした。
ところが何もかもがネットになってしまうと、こうはいかなくなってしまう。
いま不動産が高騰しているとはいえ、それは大都市圏と、地方の一部地域に限られます。また、新築マンション価格が1億円を上回るなど活況を呈していますが、今後は金利上昇も予想され、これが不動産価格どう影響する見えないところがあります。今後の不動産業界の動向は、日本経済を見極めるためにも目が離せず、それ支える不動産業者の動向はなお注目しておく必要があります。
立川昭吾の企業再生チャンネル「【不可避】街の不動産屋さん 消滅時代へ!」より