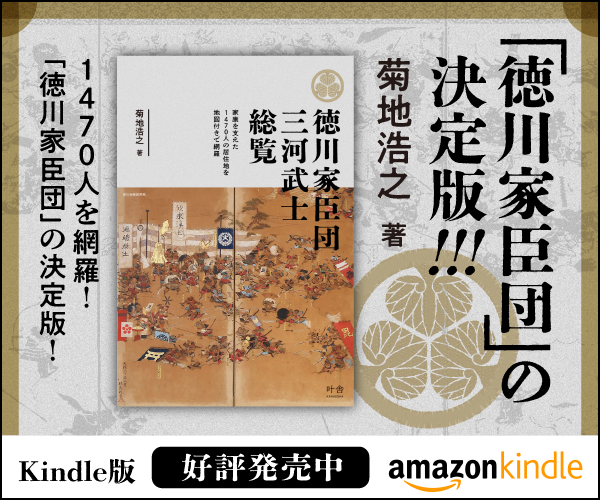1945年新潟生まれ。
中央大学商学部卒業後、東京重機工業株式会社(現株式会社ジューキ)入社。退社後は、企業の倒産現場に数多く立会い、企業の倒産回避のノウハウをマスター。1995年設立のTSKプランニングで、コンサルタントとして経営危機に直面した企業の倒産回避および事業再生に関するコンサルティングを手掛けている。
著書に『隣の会社「なぜ?」潰れないのか』『脱常識のしたたか社長論。』『日本が潰してはいけない会社』など多数。
コメにも及んできたオーバーツーリズム
今回のコメ不足の原因は、流通段階にあると農水省はいっていますが、国の備蓄米は全体の4割で、残りの6割は自由米です。しかも、備蓄米は市場に出てきていない。この残り6割のコメを、一部の業者が大量に買っている可能性があるわけです。
その背景には米価が上がるから大量に買う、不足しそうだから買うという実態があるからでしょう。

ただ、コメがここまで高騰することは国も予測していなかったことでした。
それは2024年の訪日外国人が3687万人もいて、25年は4000万人を超えるとみられているからです。
インバウンド需要が高まるなかで、日本食ブームが起こっていることもあります。たとえば、コンビニおにぎりから、寿司、ラーメン、カツカレーなんていうものまで外国人に大人気です。
単純に考えれば1か月300万人以上の人口が一気に増えているようなもので、これではコメがなくなって当たり前です。
つまり、コメを食べる人が急増したにもかかわらず、コメ市場を国がコントロールできていないということが問題なのです。
「幻の17万トン」といわれますが、国が買い付けているのは4割だけですから、残りの6割の自由取引から大口で買い付けたり、直接農家から買い取ったりということが起きている。コメ市場では、大手企業や大口需要業者によってコメの取り合いが起こっている。
昔のコメ騒動の裏はコメ問屋から始まりましたが、現代は大手飲食チェーンから始まるというようなことになっているのではないかと思います。これは断定できませんが、農水省がいっている こととは、原因が違うように私は思います。
では、新米が出てコメの流通が増えれば下がるはずの値段が下がっていない。この矛盾からは、何度も言いますが、国、農協が主食のコメをコントロールできないという実態が見えてくるのです。
2月21日に備蓄米の放出が決まりましたが、これも官邸からの圧力ともいわれています。とはいえ、実際に放出が行われてもそんなにコメ価格が下がらない可能性もあります。
いま、コメの消費市場においては流通構造の大変化が起きています。加えて、国のコメをはじめとした農業政策、インバウンド需要が高まった現在に合っているかどうかについても考える必要があります。
これまで政府は国の1番大事な根幹にあたる農業問題に対する施策が常に遅れています。
地方出身の石破首相は「楽しい日本」を作るといっていますが、石破首相の選挙区である鳥取も農業は盛んですから、首相も農業を取り巻く厳しい環境についてわかっているはずです。
一歩も二歩も遅れてしまっている農業問題に取り組むことが、石破首相のいう「楽しい日本」を作るスタートではないのかと思うのです。