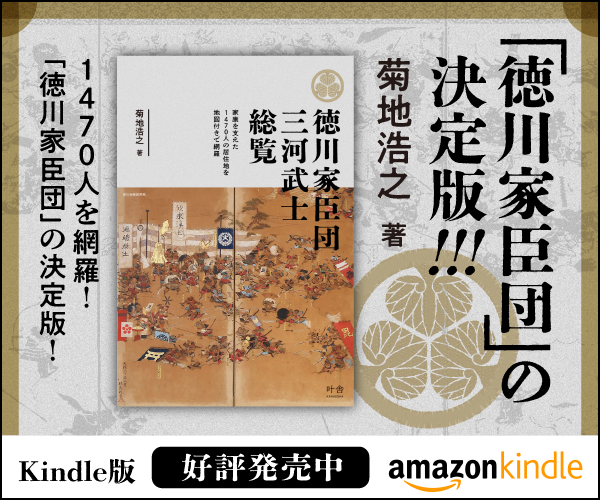1945年新潟生まれ。
中央大学商学部卒業後、東京重機工業株式会社(現株式会社ジューキ)入社。退社後は、企業の倒産現場に数多く立会い、企業の倒産回避のノウハウをマスター。1995年設立のTSKプランニングで、コンサルタントとして経営危機に直面した企業の倒産回避および事業再生に関するコンサルティングを手掛けている。
著書に『隣の会社「なぜ?」潰れないのか』『脱常識のしたたか社長論。』『日本が潰してはいけない会社』など多数。
コロコロかわる備蓄米の役割
こうした石破首相の政治信条はともかく、コメの高騰が続くなかで「100万トンも備蓄米があるのだから放出すればよいではないか」ということをよく現地で耳に しました。
そんな声に対して政府は「備蓄米の本来の目的は、災害時に迅速に食料供給をすること」とコメントしていました。
しかし、振り返ってみると、2024年1月1日に能登半島地震発生後、避難されている方たちは「コメが来ない」「コメが不足している」と近所の人が集まり、それぞれがコメを持ち寄って必死になって生活している姿が報道されていました。つまり、災害時に備蓄米が放出された形跡はなく、備蓄米が本来の目的である災害に対応したようには思えません。

当時政府は「震災の影響で、運べない、流通できなかった」という言い訳の様な見解でした。能登は半島ということもあって通じている道路が地震で寸断されてしまい、トラックで運ぶ手段がないといったこともあるでしょう。しかし、地震や災害は、交通の便のよいところだけで起きるわけではありません。災害が起こって困るところは、むしろ地方の交通の便の悪い村落です。
そうしたことに対応するマニュアルを作っておくべきではないでしょうか。空からヘリコプターや航空機を使った災害時に対応した運搬スキームを作っておかなくては、ただコメだけ集めて備蓄米にしても何の役にも立ちません。
こうした指摘を受けると、政府は「いやそれだけではない」と「コメは10年に一度不作になることがある。そして、かつては2年連続不作でも対処できる水準として政府は備蓄米を100万トン保有している」と、 「この制度に480億円予算を計上している」というのです。
新米価格は2024年10月の1か月だけで30%も上昇しています。この短期間での大幅な価格高騰で、この値上がりは異常です。
そうなれば国民は、市場にコメがないのだから備蓄米を放出してほしいというのは当然ですが、農水省は、今検討中というばかりでした。
そして、新米が出れば価格が安定するというアナウンスするのみ。これは日銀や財務省が円相場などで行う口先介入のようなもので、農水省もまさにこの口先介入をしていただけに過ぎません。しかし、その効果はなく、農水省はコメの価格をコントロールできませんでした。
減反推進派が多数を占める農水省

コメだけに限らず、農水省の施策は対症療法ばかりで、コメはもとより農業政策をどうするのかということがわれわれからは見えません。今回のコメ高騰の対策を見ていると、世論の動向だけを見てやっているんじゃないかとすら思えます。
私の出身地の新潟周辺を見ていてもわかるのですが、コメ農家はずっと減反、減反です。こうした生産調整ばかりで、政府は農家のほうを向いていない。そんな状態ですからコメ農家は、みんなやめてしまってどんどん減っていくばかりです。そして、こうした休耕田を借りて大きくしてやっている人もいるのですが、規模を大きくしても儲からないというのです。
この状態を私は、いったいどうなってしまっているのかと思っていまいます。しかも、古い話ですが、1993年の冷夏による大凶作になった平成のコメ騒動があったあとも、減反が続けられてきました。
こうしたことからも、現在の農業政策は、矛盾しているように感じます。
そうしたこともあってか、2018年度に1970年から続いていた減反政策が廃止されます。
しかし、農水省内では、いまだに減反推進派が多い。そこで表面上は「減反」は廃止したものの、コメ以外の作物に転換をさせる「水田活用の直接支払交付金制度」というものを作ります。
この「水田活用の直接支払交付金制度」は、コメをやめて、野菜などの作物に転作すれば交付金を払うという制度です。つまり、水田を潰せばお金を上げるのでコメはやめなさいと勧めているもので、減反はなくなっても田んぼを減らす政策が続いています。その予算額は3200億円で、制度としての減反はなくなっても田んぼを減らす政策の予算は減っていません。
とはいえ、この3200億円の予算はどこにいったのか、誰が使っているのかということがはっきりわかりません。これは国の農業政策が国民に全然見えない状態になっています。本来ではこうした予算がどう使われているか農家はもとより、一般国民もわかるようでなければなりません。