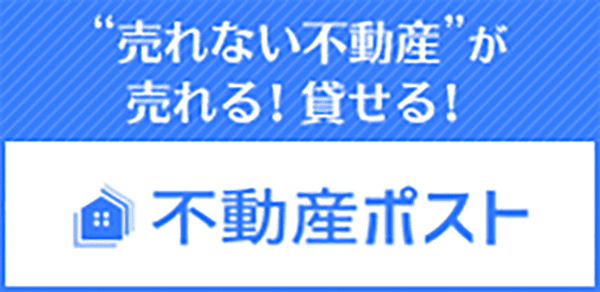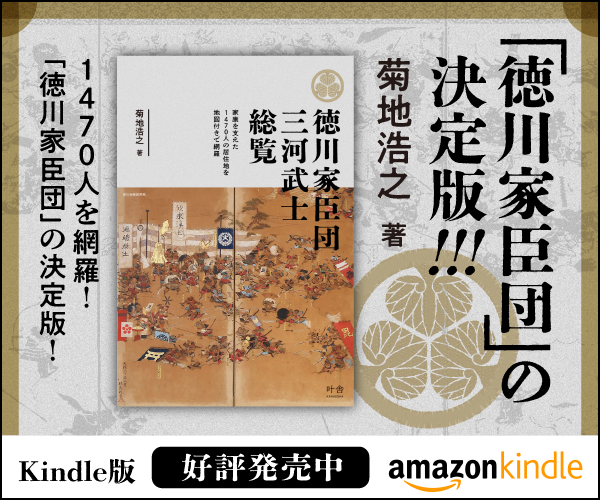北里大学薬学部卒業後、大学病院、企業診療所、透析施設で薬剤師として勤務。その後、製薬会社で企画販売に従事し、体調を崩した時に漢方薬に出会い、漢方を学びはじめる。日本漢方協会漢方講座を経て、田畑隆一郎先生の無門塾入門、愛全診療所 蓮村幸兌先生(漢方専門医)の漢方外来にて研修。現在は「より健やかに、更に美しく」を目指して患者さんの漢方相談、わかりやすい漢方の啓蒙活動に取り組んでいる。著書に『更年期の不調に効く自分漢方の見つけ方』(ごきげんビジネス出版)がある。
くしゃみ、鼻水、鼻つまりの三大症状は水の代謝や排泄が正常に行われていない状態のことで漢方では「水毒」を呼ばれています。
なかでも花粉症の場合は、鼻や気管支に「水」が蓄積されていると考えられますので、余分な「水」をさばく漢方薬を用います。そして、どのような漢方薬を用いるかは、それぞれの体質や症状により異なります。
花粉症は、三大症状に悩まされるだけでなく集中力も低下するといったこともあるため、眠くならない漢方薬で乗りきりましょう。
サラサラ鼻水が止まらない「寒証タイプ」
寒証タイプの花粉症は 水毒に寒証(からだに寒邪が侵入することにより冷える状態)が結びつくことが原因です。
このタイプの特徴は、寒気を伴う「水のようなサラサラした鼻水」が止まらない、鼻汁は無色という点です。
対応策は、からだを温めながら水代謝を改善する漢方薬を用いますが、冷えは症状を悪化させるため、薄着をしないことも重要です。
*小青竜湯 (ショウセイリュウトウ)
【体質と主な症状】やや体力のある方/くしゃみ、鼻水、鼻つまり
【特徴】水様性の鼻水やくしゃみの第一選択薬で花粉症の初期に多く用いられる漢方薬です。サラサラした無色透明の鼻水、鼻がムズムズしてくしゃみが1日に何度もでる、体が冷えると症状がひどくなる、朝起きてからくしゃみがひどい、お腹をたたくとぽちゃぽちゃ音がすることがあるなどがよくみられます。
【成分の効能】麻黄(マオウ)と桂枝(ケイシ)で体の外から侵入する冷えた邪(寒邪)を温めながら発散させ、細辛(サイシン)、乾姜(カンキョウ)、半夏(ハンゲ)、五味子(ゴミシ)で肺を温めながら水分循環を促し余分な水分を体から排出することで症状を改善します。
*苓甘姜味辛夏仁湯 (リョウカンキョウミシンゲニントウ)
【体質と主な症状】体力のあまりない方/冷え症で鼻水、咳、薄い水様の痰
【特徴】肺の水はけが滞ったために起こる鼻炎に効果があります。麻黄が含まれていないため胃腸が弱っている場合や、体力のない高齢の方に使いやすい漢方薬です。
【成分の効能】甘草(カンゾウ)、乾姜、細辛で肺を温め、茯苓(ブクリョウ)、半夏で水をさばくことで鼻水が軽減し、五味子、杏仁(キョウニン)が咳や痰を改善します。