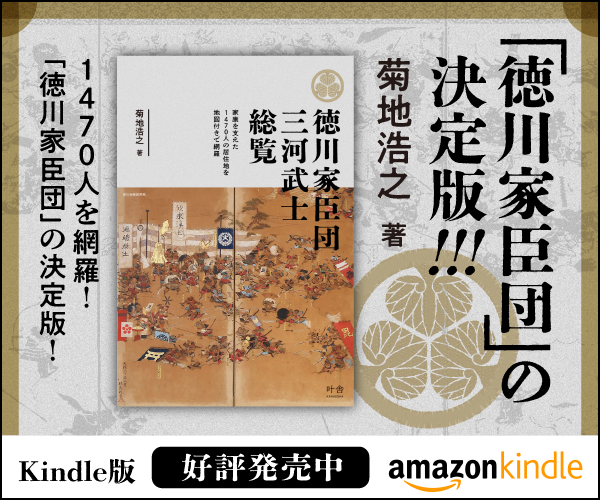1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

また、借地借家人が取り消せる契約には「解約後賃料の5倍の損害金を払う」など借家人に不利益になる約定は無効になる。
帰ってくれない、帰してくれない
「不退去型契約/監禁型契約」
自宅を訪れた事業者に対し、退去を求めたのに退去しないで契約をさせられた場合や、事業者の事務所などに呼ばれ自分は帰りたいと伝えたのに帰しせてもらえず契約をさせられた場合といった契約も取消すことができると定めている。
「明渡し約束」
借家契約の更新期に家主が自宅にやってきて、「今回は更新するが次回には更新しないのでそのことを契約書に書き入れてくれ、書かないのであれば更新しない」と要求されるケース。
そこで「借家人は、よく考えて返事するから帰ってくれ」伝えたが、家主は「今、了解しないのなら更新はしない」と迫り、困り果てて家主の言とおりに契約書に印を押してしまった。
これは、不退去型の困惑契約にもなるので、借家人は取消すことができる。
そもそも契約そのものが成り立たない契約条項
消費者契約法は、消費者に不当な不利益を与える契約条項は無効であると定めている。
たとえば、借家契約書に「賃貸借契約解除後立ち退くまでの間、契約家賃の5倍の損害金を支払う」ということが明記されていたとする。このような損害金条項については、「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、超える部分については無効」とされている。
何が平均的な損害の額かは明確ではないが、新規に賃貸した場合の賃料額というにが目安になる。
また、賃料滞納した場合、滞納賃料に年20%の遅延利息を付すという条件があった場合も、消費者契約法では上限を14.6%としているので、これを超える部分は無効となる。
不動産会社もオーナーと同じ
消費者に誤認をさせる、困惑させることは事業者本人ではなく、事業者から契約委託を受けた、あるいは代理人が同じことをすれば、事業者が行ったのと同様に契約を取消すことができる。
借地借家の場合は、不動産仲介業者が地主、家主の代理人となることが多いが、こうした不動産仲介業者も同様に扱われる。
ただし、消費者の契約の取消権の権利行使には時間の制限がある。
その期間は不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知の場合は消費者が誤認したことに気付いたときから、不退去、監禁の場合は不退去、監禁が終わったときから、6か月以内に取消さなければならない。また、契約してから5年が経つと無条件で取消すことができなくなるので注意が必要だ。