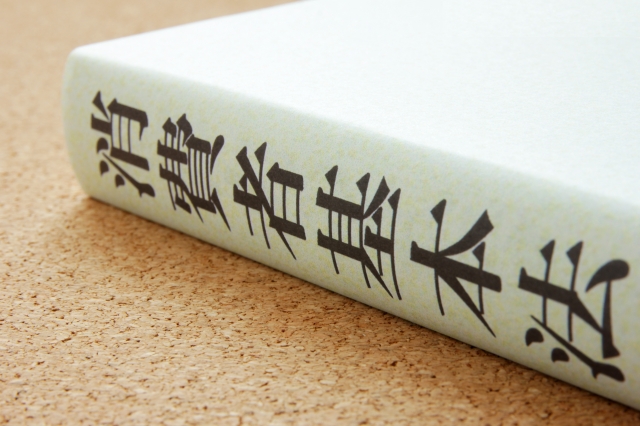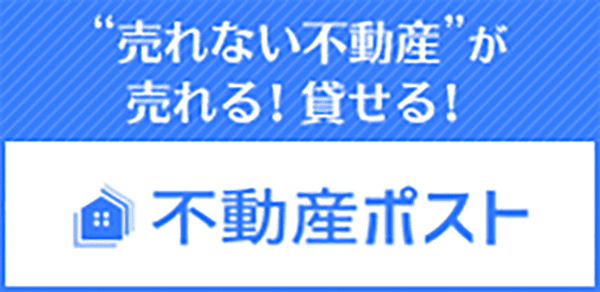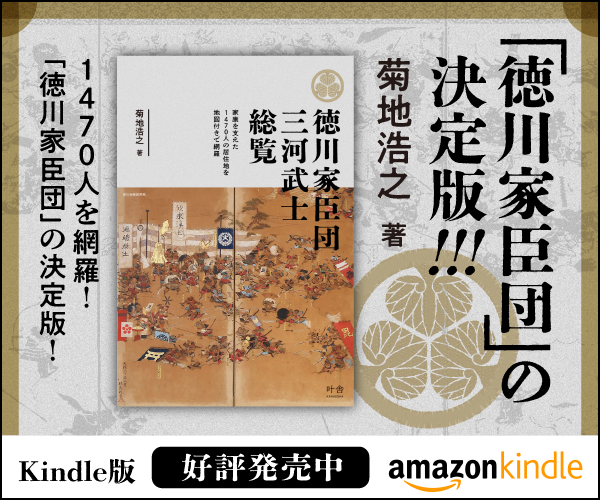1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。
「消費者契約法」とはどのような法律か?
昨今、外国人によって買われた賃貸住宅の家賃が突然、一方的に大幅に値上げするという通知が行われトラブルになるケースが増えている。
こうした問題に対抗する方法はないのか。
その対抗策の1つが消費者契約法だ。
2001年4月1日に施行された消費者契約法は、契約における「消費者」と「事業者」の関係を整理し、消費者を不当な取引から守るために制定された法律。この法律の最大の特徴は、「消費者」と「事業者」を明確に定義した点にある。
「事業者」とは、以下にようなものを指す
1)「法人その他の団体」
2)「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」
という2つで、それ以外の個人はすべて「消費者」となる。
「事業」とは、一定の目的をもった同種の行為がくり返し行われるものとされ、営利を目的としているかの有無は問われない。この定義は非常に広く、国も「事業者」になりえる。
そこで消費者と事業者の間でなされる契約を「消費者契約」ということになる。
この「消費者契約」というのは、個別の売買契約、工事請負契約とは別の次元になり、個別の契約の上に消費者契約という網をかぶせるものである。
借地借家人は「消費者」
しかし、少しややこしいのが借地借家契約と消費者契約の関係で少し説明を要する。
借地借家契約と消費者契約の違いは次のようになる。
個人の家主と個人の借家人が住居目的で借家契約をした場合、家主は事業として貸家契約をするので「事業者」になる。一方、借家人は個人で、しかも事業のための借家契約ではないので、「消費者」になり、この借家契約は「消費者契約」となる。
では、次のようなケースはどうだろうか。
個人の家主と、個人の借家人が店舗目的で借家契約をした場合。
この場合は、借家人は個人だが、店舗営業という事業のために借家契約をするので「消費者」には該当せず、この借家契約は「消費者契約」にはあたらない。