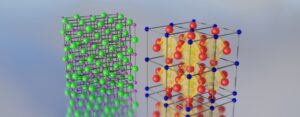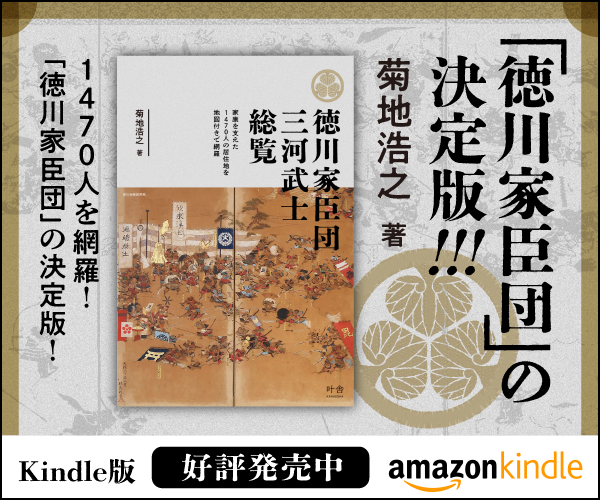1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。
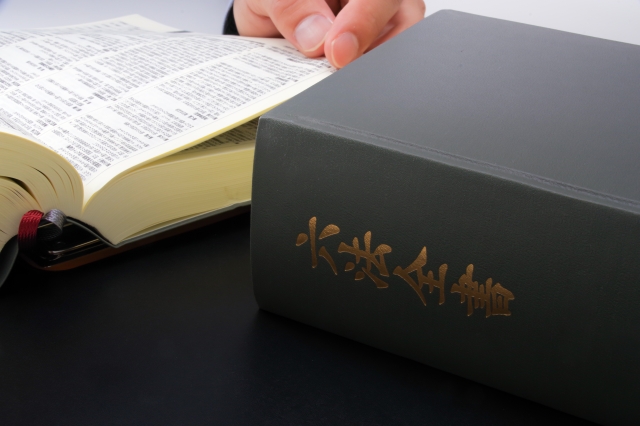
そこで、この事例では、賃貸人が3年間にわたり滞納を一度も通知せず、結果として損害を拡大させることになってしまった。
こうした行為は「信義則」に著しく反するもの。過去の裁判例でも、貸主が保証人に滞納事実を通知せずに損害が膨らんだ場合、その全額を保証人に請求するのは、権利濫用に当たると判断されてきた。したがって、このケースでも保証人が全額を負担する必要はないと考えられる。
さらに、賃貸人の怠慢が損害拡大の一因である以上、むしろ貸主側がその責任を負うべきだといえる。保証人は必要に応じて、信義則を根拠に裁判所に訴え、責任の範囲を制限してもらうことも可能だ。
保証人になるとすべて失うのは昔の話?
2020年4月に施行された改正民法では、保証人保護の規定が強化された。
特に注目すべきは民法第458条の2にある「情報提供義務」である。これにより、貸主は賃借人が家賃を滞納したことを知った場合、2か月以内に保証人へ通知しなければならないとされている。
もしこの通知を怠った場合、通知がなされていれば発生しなかったはずの遅延損害金については、保証人に請求できなくなる。
つまり、長期間の滞納を放置したケースでは、膨大な遅延損害金が削除され、保証人の負担が軽減される可能性があるというわけだ。
今回の事例が2020年以降の契約であれば、保証人の立場はさらに守られる。
昔のテレビドラマなどでは、連帯保証人になったことで、債務保証を求められ一家離散というような描かれ方をしていた。
連帯保証人は厳しい責務を負う立場に変わりはない。しかし、賃貸人が信義則に反して報告義務を怠った場合や、改正民法に違反して貸主が情報提供を怠った場合には、保証人の責任は制限される。
今回のケースでは、賃貸人が3年間も通知をせず、結果として損害を拡大させている。保証人はこの事情を根拠に、支払義務の全額を否定できる可能性が高い。必要であれば裁判所の判断を仰ぐというのも1つの方法といえる。
とはいえ、連帯保証人の責任が重いことに変わりはない。連帯保証人になる際は、くれぐれも慎重さが必要だ。