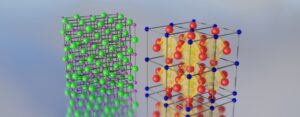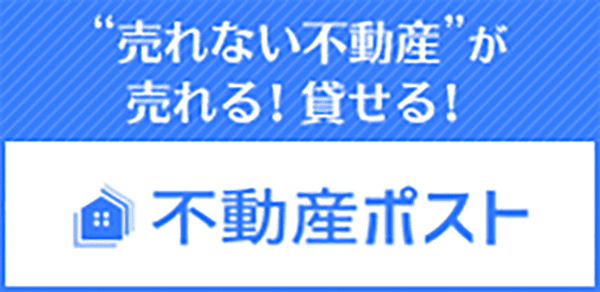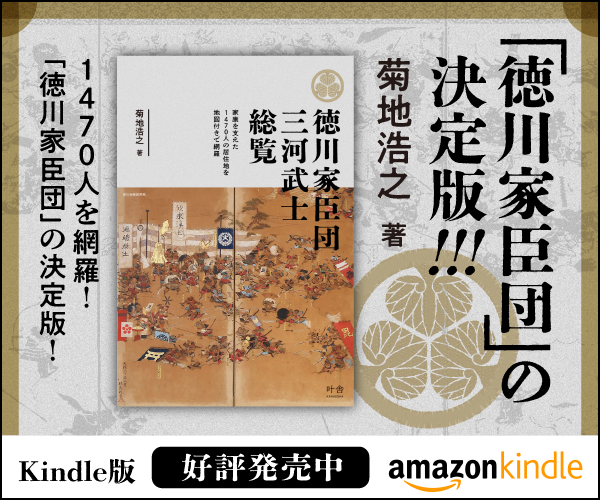1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。
家賃を滞納、連帯保証人の法的責務
賃貸借契約における「連帯保証人」という立場は、時に想像以上に重い責任を伴う。店舗や事業用物件の契約においては、保証金や敷金が高額に設定されいることもある。しかし、それでもなお保証人を求められることがある。その際にどのような法的リスクがあるのか、保証人の責務はどの範囲まで及ぶのかを理解しておくことは重要である。
あるケースでは、店舗の連帯保証人となっていた人物に対し、賃借人が退去した後に3年分の滞納家賃の請求が賃貸人から届いた。保証金として契約時に300万円を差し入れていたが、総額580万円の滞納が発生したため、差し引き280万円の請求を受けたという。
それまでの3年間にわたって賃貸人から一度も滞納の報告を受けていなかったという。
このような状況で、保証人は本当に全額を支払う義務があるのだろうか。
民法第447条では、連帯保証人の責務の範囲を「主たる債務に関する利息・違約金・損害補償、その他すべてその債務に従いたるものを包含する」と定めている。そのため連帯保証人は賃借人とほぼ同等の責任を負うことになる。しかも通常の保証契約に認められる「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」も連帯保証人には認められていないため、連帯保証人は極めて厳しい立場に置かれる。
賃貸人と貸主側の責任は?
その一方で、保証契約は賃貸人と保証人との直接の契約関係であり、双方には誠実に契約を履行する義務である「信義誠実の原則(信義則)」がある。
わかりやすくいうと、賃貸人は、保証人に対して賃借人の滞納状況や経営の悪化を適切に報告する義務を負うとされる。というのも、これを怠れば、保証人に過大な損害を押し付けることとなり、信義則違反とされる可能性が高いなるからだ。