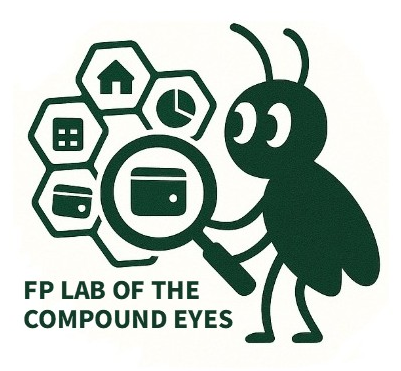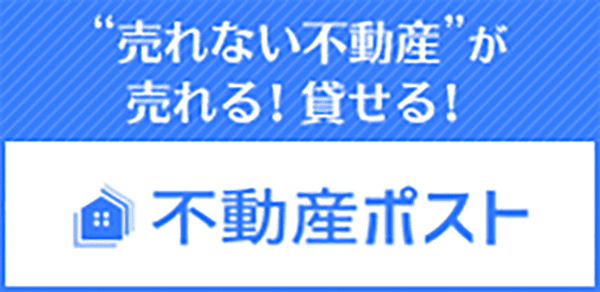マクロ経済の潮流から日々の暮らしに寄り添うお金の話まで――複眼的な視点で「生活」と「ファイナンス」を読み解く実践的チーム。メンバーは、生活者のリアルを綴るライター、現場感覚を持つファイナンシャルプランナー、そして個人に最も近い立場でライフリスクと向き合う生命保険・損害保険の営業パーソン。異なる立場と経験から、単なる数字や制度にとどまらない“生きた情報”を発信している。
賃貸人の地位は自動的に承継される
住んでいる部屋のオーナーが代わり、家賃値上げに関連したトラブルが社会問題となっている。そんなオーナーチェンジで起きるトラブルには敷金に関係したものもある。
「この建物を購入し、新しい家主になりました。なお、私は敷金を受け取っていないので、改めて納めてください」
家賃値上げと同じようにこんな文書が突然届くのだ。
普通に生活している中で、物件のオーナーを意識することは多くはない。しかし、オーナーが代わるといわれればどんな人か不安に思うのは当然こと。そんな中でこんな文書が送られてくれば、払わなくてはいけないのかとさらに不安が大きくなるだろう。
しかし、結論からいうと敷金を再び支払う必要はない。というのも、民法で借主の権利を保護する仕組みを整えているからだ。
民法(第605条の2)では、建物の所有者が変わっても、借主がすでに住んでいる限り、賃貸契約はそのまま新しい家主に引き継がれると定められている。
つまり、家主が代わっても、契約内容は何ひとつ変わらない。家賃を受け取る権利も、修繕や敷金返還といった義務も、すべて新家主が引き継ぐことになる。
敷金は、借主が将来の未払い家賃や原状回復費に備えて差し入れる「預け金」のようなものだ。引っ越す際は、未払い分などを差し引いた残りを返してもらう約束のものである。
当然のことながら、この返還義務も新しい家主に自動的に引き継がれる。したがって、家主が代わったからといって、敷金をもう一度払う必要はまったくない。
「敷金を受け取っていない」は家主同士の問題
それでも新しい家主が「旧家主から敷金を受け取っていない」と言ってくることがある。
このとき、多くの借主は「では、やはり払わなければならないのか」と不安になる。
だが、これは新旧家主のあいだの精算の問題にすぎない。
不動産の売買では、決済の際に旧家主が預かっている敷金相当額を売買代金から差し引くか、別途で清算するのが一般的。仮にそれを怠ったとしても、それは家主どうしの内部の問題であり、借主には一切関係がない。
法律上、敷金は自動的に新家主に承継される。借主が二重に支払う義務はないのである。
とはいえ、そんなことを頭ごなしに、新しいオーナーに言ってはトラブルになりかねない。オーナーだからといって、不動産、ましてや法律については詳しくない人も多い。単に投資目的や、最近ではオーナーが外国人ということも珍しくなくなっている。もし新しい家主から敷金の再納付を求められたら、まずは冷静に対処したい。
契約書や領収書など、旧家主に敷金を支払った証拠を提示し、「敷金はすでに支払い済みであり、その関係は法律により引き継がれています」と伝えることがポイントだ。
きちんと法律(民法第605条の2)をしめすことで、説得力も増す。
それでも理解を得られない場合は、旧家主に連絡して敷金精算の有無を確認してもらうのがよい。
どうしても話がこじれるようなら、消費生活センターや弁護士など専門家に相談するのも一つの方法だ。無理に要求に応じる必要はなく、あくまでも借主である自分は法的に守られる立場にあることを伝えるようにする。
主が変わることは、いまや珍しいことではない。
しかし、こうした「よくある出来事」ほど、知らないと損をしやすいのも事実。敷金は決して消えてしまうものではなく、引っ越しの際に変換されることが前提のもので、オーナー間どうしの契約とともにに引き継がれるものなのだ。
法律は、こうした日常のトラブルから生活者を守るためにある。もし突然「敷金をもう一度」と言われても、慌てずに対応すれば大丈夫だ。
家主が変わっても、借主の安心は変わらない――。それが民法の定める「暮らしのルール」なのである。