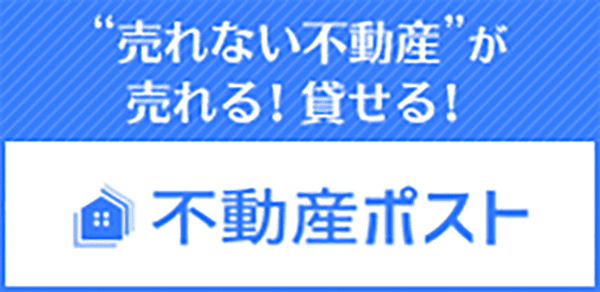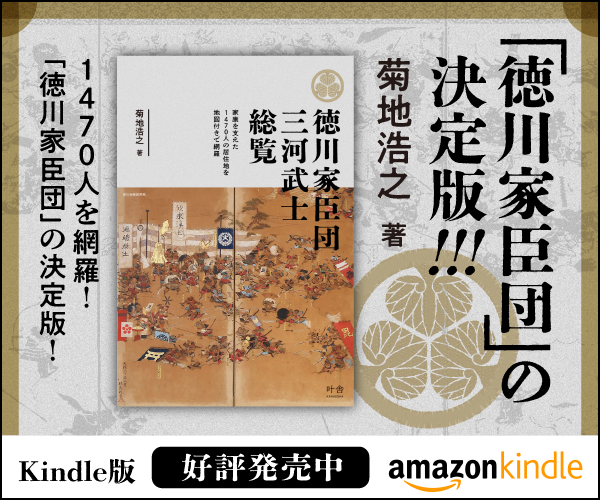1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。
用途と法的根拠
まず、用途の違いである。
保証金は事務所、店舗、テナントなど法人契約で用いられることが多い。一方、「敷金」は個人の住宅賃貸契約で使われる。
精算方法では保証金は退去時に「敷引き(解約引き、償却とも呼ばれる)」がある契約形態が一般的だ。これに対して、敷金には敷引きがなく、原状回復費などの実費精算になる。
また、法的な位置づけにも差がある。
保証金は法律上の明文規定が存在しない。しかし、敷金は民法第316条、第619条などで規定され、2020年4月施行の改正民法第622条の2により定義や返還義務、充当に関しても明文化された。これにより敷金の法的位置づけが明確にり、判例上、敷引きのない保証金は敷金と同様に扱われ、民法の敷金規定が類推適用される。
加えて、承継の有無も異なる。
保証金は契約に定めがない限り新しい家主に引き継がれないのに対し、敷金は原則として新しい家主にも承継される。
また、保証金を「敷金+礼金」とみなす解釈もある。保証金方式では敷引きがある代わりに礼金を取らないことが多く、敷金方式では敷引きがない代わりに「礼金」を徴収する地域が多い。
名称よりも大切なその中身
以上のように「保証金」「敷金」にそれぞれに用途や法律的な裏付けがあるが、実務上は名称よりも契約内容が重要である。
例えば「保証金」と記載されていても、その金銭が債務担保目的で預けられ、原則返還されるものであれば敷金と同じ性質を有すると判断される。重要なことは、名称に惑わされず、契約条項を精査することである。特に事務所や店舗の賃貸では、保証金額や償却条件、承継条項が経営上のコストやリスクに直結するため注意したい。
近年の法改正により、敷金は定義から返還義務まで明確なルールが適用されるが、
保証金には今も法律上の直接規定はない。しかし、判例が示すように、名称が「保証金」であっても、その契約内容が「債務を担保する目的で預けられ、原則として返還されるべき金銭」である場合、その性質は民法上の「敷金」と実質的に同じであると判断される。
このような場合、民法の敷金に関する規定が類推適用(類似の事柄についてのルールをあてはめること)されることになる。
したがって、「敷引きのない保証金」は、法的にはほぼ「敷金」として扱われる。