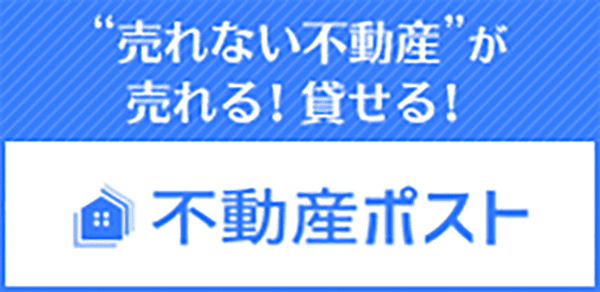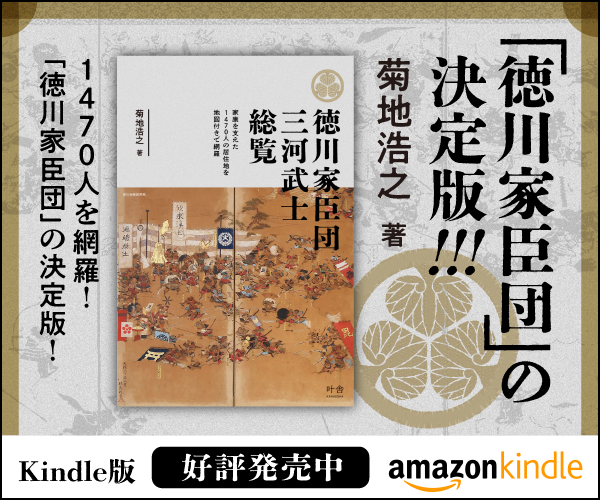北里大学薬学部卒業後、大学病院、企業診療所、透析施設で薬剤師として勤務。その後、製薬会社で企画販売に従事し、体調を崩した時に漢方薬に出会い、漢方を学びはじめる。日本漢方協会漢方講座を経て、田畑隆一郎先生の無門塾入門、愛全診療所 蓮村幸兌先生(漢方専門医)の漢方外来にて研修。現在は「より健やかに、更に美しく」を目指して患者さんの漢方相談、わかりやすい漢方の啓蒙活動に取り組んでいる。著書に『更年期の不調に効く自分漢方の見つけ方』(ごきげんビジネス出版)がある。
尿トラブルの主な症状は膀胱炎、尿もれ、頻尿がありますが、人には相談しにくく、悩みながらも対応に悩んでしまうものです。
現代医学的には細菌感染による炎症(膀胱炎、尿道炎)や心因性、代謝異常によるものと考えられており、細菌感染が原因の場合には抗菌薬が度々処方されます。しかし、心因性、環境、体質、加齢等も関わると排尿時痛などの不快な症状や残尿感、頻尿などがなかなか改善されないことが多くみうけられます。
男性は尿道が長いため排尿時間が長く排尿後の滴下、いわゆる「追っかけ漏れ」が起こりやすく、また加齢に伴う前立腺肥大により尿道が圧迫され残尿感が引きおこりやすくなります。
一方、女性は尿道が短いため細菌が侵入しやすく膀胱炎をおこしやすい、また出産や加齢による骨盤底筋のゆるみや過緊張が影響するともいわれています。
東洋医学において尿トラブルは、下腹部の水分代謝の異常と考えます。症状や原因を探りながら漢方薬で回復を図りましょう。
水毒①(湿熱:膀胱内に溜まった熱)タイプ
痛みや炎症を伴う膀胱炎や尿道炎
頻尿、残尿感などが特徴で、排尿後の痛みや不快感、尿道の熱感を伴うこともあります。
水の巡りを正常化させ、さらに熱を取り除くような漢方薬を用います。
*猪苓湯(チョレイトウ)
【主な症状】トレイの回数が多い、排尿後の軽い痛み、残尿感、下半身がむくむことがある
【効果】水分代謝を高めて尿を増やして洗い流す力を高めることで症状を改善します。
【成分の効能】猪苓(チョレイ)、茯苓(ブクリョウ)、沢瀉(タクシャ)で水をさばき、滑石(カッセキ)は尿路の熱や炎症を去り、阿膠(アキョウ)はからだに栄養を与え止血にも働きます。
*竜胆瀉肝湯(リュウタンシャカントウ)
【主な症状】排尿後の強い痛み、尿は少なく濃い、尿がにごる、陰部の痒みを伴うことも、イライラしやすい方に
【効果】からだの余分な熱を去り、水の巡りを正常に調えながら炎症や痛み、痒みを改善します。
【成分の効能】竜胆(リュウタン)、黄芩(オウゴン)、山梔子(サンシシ)で熱を取り除き、沢瀉、車前子(シャゼンシ)、木通(モクツウ)で余分な水分を取り除き、当帰(トウキ)、地黄(ジオウ)で血を補い体の回復力を高めることで症状を改善します。